映画にはハリウッドをはじめ、フランスに代表されるヨーロッパ映画、中国、韓国などのアジア映画、あまり馴染みのないところではチェコやインドなど、国によって様々な特色がある。
しかし現在ではネットによる情報化もあって、多種多様な映画が世界中で撮られている。また様々な国同士による合作映画も一般的なものとなり、一概にその国の映画の特徴を語ることはできないが、その国の文化や歴史が映画に反映されることは非常に多い。そうした国ごとの映画の特徴を紹介するので、興味がある人は映画を選ぶ参考程度に読んでもらいたい。
好みの映画に出会える確率が少しは高くなるはずだ。
Contents
欧米
アメリカ(ハリウッド)映画
 アメリカ映画と言えば、まず連想するのがハリウッド映画だが、実際アメリカ映画という言葉は同義語として使われる。しかしアメリカの映画会社がハリウッドに集中しているだけで、もちろん非ハリウッド映画も多く製作されている。例えば、制作費が小規模なインデペンデント映画なんかは非ハリウッド映画の場合が多い。
アメリカ映画と言えば、まず連想するのがハリウッド映画だが、実際アメリカ映画という言葉は同義語として使われる。しかしアメリカの映画会社がハリウッドに集中しているだけで、もちろん非ハリウッド映画も多く製作されている。例えば、制作費が小規模なインデペンデント映画なんかは非ハリウッド映画の場合が多い。
ハリウッドという映画のメッカがあるので、製作本数、規模ともに世界でトップというのがアメリカ映画最大の特徴である。それ故、国特有の映画の特徴を語るのは最も難しいのがアメリカ映画でもある。
もう一つ大きな特徴としてアメリカにはアカデミー賞があることも挙げられる。またそれもアメリカ特有の映画の特徴をぼかしてしまう要因となっている。というのも昨今アカデミー賞の選考が、その年の世界の映画賞を参考にしている傾向があるからだ。アカデミー賞までにその年の賞レースを勝ち抜いてきた話題性のある作品が選ばれる傾向にあるので、意外と特徴が見えづらいのがアカデミー賞である。ただ一つ注意してもらいたいのが、アカデミー賞の対象となるのは英語の作品ということだ。それ以外の作品は外国語映画賞にカテゴライズされる。
多種多様な作品が存在するのがアメリカ映画だが、ハリウッド映画のいわゆる超大作や俳優の高額なギャラは話題性も高く日本人としては馴染みやすい。
フランス映画
 ヨーロッパ映画と言えばまず出てくるのがフランス映画。世界三大映画祭のひとつ、カンヌ国際映画祭開催の地としても知られる。また映画が発明された国でもある。映画創成期、フランス映画の技術は世界一を誇っていた。映画の歴史という意味ではアメリカ(ハリウッド)より重要な国である。
ヨーロッパ映画と言えばまず出てくるのがフランス映画。世界三大映画祭のひとつ、カンヌ国際映画祭開催の地としても知られる。また映画が発明された国でもある。映画創成期、フランス映画の技術は世界一を誇っていた。映画の歴史という意味ではアメリカ(ハリウッド)より重要な国である。
世界初の女性監督が誕生したことや、1908年の映画を芸術に高めようという運動、1950年代末には「新しい波」を意味するヌーベルバーグというムーブメントが起こったことからも、映画という文化に対して常に新しい解釈を模索してきた国である。特にヌーベルバーグは現代の映画においてもよく引き合いに出されるほどの大きな流れであった。
また、フランスはヴェルサイユ宮殿を建設したルイ14世の時代からあらゆる芸術的文化が発展してきた国であり、「芸術の都」と呼ばれるパリに代表する華やかな空気は、現在のフランス映画にも見られる。
フランス映画の特徴は大きく2つあると思う。一つは日本でも大ヒットした『アメリ』(2001)のようなポップな華やかさを持つ作品、もう一つはヌーベルバーグの流れを持つ芸術的で難解な作品である。
ヌーベルバーグを代表する監督ジャン=リュック・ゴダールの再来とされるレオス・カラックスは、ヌーベルバーグ以降のフランス映画に「新しい波」をもたらしたと言われる。カラックスを代表する三部作『ボーイ・ミーツ・ガール』『汚れた血』『ポンヌフの恋人』はその難解さ、芸術性の高さ、斬新さ、あらゆる面でフランス映画らしいと言える。
ドイツ映画
 僕はドイツ映画というと悲しいイメージがある。映画という文化の発展がここまで社会情勢に翻弄された国は世界でも類を見ない。ドイツではナチス以前から映画はプロパガンダとして重要な役割を担ってきた。第二次世界大戦末期にはヒトラーが反ユダヤや愛国心を煽るプロパガンダ映画をさらに推進していくこととなる。
僕はドイツ映画というと悲しいイメージがある。映画という文化の発展がここまで社会情勢に翻弄された国は世界でも類を見ない。ドイツではナチス以前から映画はプロパガンダとして重要な役割を担ってきた。第二次世界大戦末期にはヒトラーが反ユダヤや愛国心を煽るプロパガンダ映画をさらに推進していくこととなる。
プロパガンダがドイツ映画の発展の一翼を担っている反面、ヒトラー政権下では多くの映画人が国外に亡命し、ドイツ映画の発展を妨げた側面もある。第二次世界大戦敗戦後は冷戦により東西に分裂したこともドイツ映画に大きな影響をもたらした。
西ドイツでは映画産業は黄金期を迎え、ニュー・ジャーマン・シネマという芸術性に重きを置いた新しいドイツ映画を作り上げる運動が起こった。東ドイツではソ連によって社会主義を推進するようなプロパガンダ映画が製作されることとなる。これにより世界的に評価される映画の多くは西ドイツの映画であった。
1951年、この頃に世界三大映画祭の一つ、ベルリン国際映画祭が開催されるのだが、これは東側が西側に芸術文化をアピールしたいという政治的意図によって始まった。今では世界三大映画祭で唯一ベルリンという大都市で開催されることもあって世界最大規模の映画祭となっている。また、ドイツのこうした歴史からベルリン国際映画祭は社会派の作品が集まる傾向が強いという特徴がある。
ドイツ映画自体も社会派の要素を含む作品が多い。ドイツの歴代興行収入を塗り替えた大ヒット作『グッパイ、レーニン!』(2002)は東西ドイツ統合後の庶民の身に起こった悲喜劇を家族像と共に描いた作品であったし、アカデミー賞外国語映画賞を始め世界の映画祭で評価された『善き人のためのソナタ』(2006)も、当時の東ドイツが置かれていた監視社会の実像を克明に描いている。また、ヒトラーを題材にした映画が非常に多いのは言うまでもないかもしれない。
ナチスによるプロパガンダ映画として発展してきた歴史は同時に、今もホロコースト(大量虐殺)映画のテーマとして世界で最も多く扱われている。歴史の呪縛からなかなか解放されないのがドイツ映画の皮肉な特徴だ。
イタリア映画
 ドイツ映画がヒトラーの独裁政権に翻弄されたように、イタリア映画も同じような境遇を経験している。しかし、ムッソリーニによるファシズム体制(独裁政権)によってプロパガンダ映画が製作されたものの、イタリア映画は独裁政権の影響をあまり受けなかったという意味では幸運である。そればかりかファシズム体制によって作られた映画都市チネチッタでは今でもイタリア映画の多くが製作されている。
ドイツ映画がヒトラーの独裁政権に翻弄されたように、イタリア映画も同じような境遇を経験している。しかし、ムッソリーニによるファシズム体制(独裁政権)によってプロパガンダ映画が製作されたものの、イタリア映画は独裁政権の影響をあまり受けなかったという意味では幸運である。そればかりかファシズム体制によって作られた映画都市チネチッタでは今でもイタリア映画の多くが製作されている。
さらにイタリア映画を語る上で重要な運動であるネオレアリズモは、ファシズム体制に抵抗する形で生まれた。ネオレアリズモとは、内戦による恐怖と破壊を経験した後で未来を築こうとあえいでいたイタリア社会に現れた問題をテーマとし、現実主義でこれを描いた映画である。テーマには派閥主義、インフレ、失業などがあり、ネオレアリズモの代表作と言えばヴィットリオ・デ・シーカ監督の『自転車泥棒』(1948年)が有名である。
経済が回復しイタリアが繁栄し始めると、ネオレアリズモのような現実主義は次第に薄れていき、ピンク・ネオリアリズモと呼ばれるイタリア式コメディや、世界中に根強いファンがいる『荒野の用心棒』『夕陽のガンマン』『続・夕陽のガンマン』などのマカロニ・ウェスタンといったイタリア映画独特のジャンルが生まれる。
1970年代後期、イタリア映画の中でも芸術性の高い作品は変わらず評価も高かった。エルマンノ・オルミ監督の『木靴の樹』(1978)はカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞しているがこれらの作品はイタリア映画の中で孤立した存在となっていた。1980年頃にはイタリア映画の主流は芸術性のない娯楽作品となり、停滞していくこととなる。
そして1990年代、イタリア映画の復活を印象付けた作品がジュゼッペ・トルナトーレ監督の『ニュー・シネマ・パラダイス』(1990)であり、ロベルト・ベニーニ監督の『ライフ・イズ・ビューティフル』(1998)だった。また2000年代にはナンニ・モレッティ監督の『息子の部屋』もパルムドールを受賞している。これらの作品はネオレアリズモのような現実主義を感じさせる重たいテーマに挑んだ作品だった。
イタリア映画は芸術性を増す程に世界で評価され、それこそがイタリア映画の真骨頂である。世界三大映画祭の一つ、ベネチア国際映画祭が芸術性に優れた映画祭と言われる由縁である。
イギリス映画
 英語圏ということもあり、古くからアメリカ(ハリウッド)映画と闘いを強いられてきたイギリス映画。そのためか大衆的なアメリカ映画的な作品も多く、日本人はイギリス映画をアメリカ映画と思っていることも少なくない。イギリス映画で最も有名な『007』シリーズは基本的にはイギリス映画だが、アメリカとの合作やアメリカ映画の作品もあるので、こうした勘違いを象徴したような作品である。
英語圏ということもあり、古くからアメリカ(ハリウッド)映画と闘いを強いられてきたイギリス映画。そのためか大衆的なアメリカ映画的な作品も多く、日本人はイギリス映画をアメリカ映画と思っていることも少なくない。イギリス映画で最も有名な『007』シリーズは基本的にはイギリス映画だが、アメリカとの合作やアメリカ映画の作品もあるので、こうした勘違いを象徴したような作品である。
また、イギリス映画を語る上で外せないのが階級制度だ。決して法律で定められた制度ではないが、先進国でありながら国民の意識の中に階級社会というものが根付いている。どこの国でも階級制度という概念は少なからず存在しているが、イギリスの階級制度は経済的な区分ではなく、家柄、学校、スポーツ、職業 に至る生活のあらゆる領域で浸透している。上流階級、中流階級、労働階級の3つに分類されるが、大衆文化である映画は最も多い労働階級者たちのものだと言える。
そんな労働階級者たちにとって辛い日々の糧となるのが映画だったことから、イギリスではコメディ映画が好まれる傾向がある。『フォー・ウェディング』(1994年)『ノッティングヒルの恋人』(1999年)などのロマンティック・コメディは日本でも御馴染みだ。また、『フル・モンティ』(1997年)のような労働階級者をテーマにしたコメディも人気がある。
興行的な面ではこれらの作品に負けるが、ケン・ローチ監督を代表する社会派映画がイギリス映画の真骨頂である。労働階級者の抱える問題をリアルに映した作品はアメリカ映画とは一線を画すイギリス映画ならではのものだ。ただ、労働階級者たちにとって現実と闘う唯一の術はユーモアであるため、イギリス映画の多くはユーモアを忘れない。
ロシア映画
 国家と映画が最も密な関係なのがロシア映画である。ソビエト時代、レーニンは「すべての芸術の中で、もっとも重要なものは映画である」という考えからプロパガンダとして映画を利用し、後のスターリン独裁政権下でもそれは同様であったが、アメリカ(ハリウッド)映画へ対抗するため国策として発展してきたという側面もある。
国家と映画が最も密な関係なのがロシア映画である。ソビエト時代、レーニンは「すべての芸術の中で、もっとも重要なものは映画である」という考えからプロパガンダとして映画を利用し、後のスターリン独裁政権下でもそれは同様であったが、アメリカ(ハリウッド)映画へ対抗するため国策として発展してきたという側面もある。
ロシア映画は大きく分けると2つある。社会主義時代のソビエト映画と、ソビエト崩壊後の資本主義にシフトしたロシア映画だ。ソビエト崩壊後は10年以上の間に渡り映画製作がほとんど行われなかったため、ロシア映画史には明確な区切りが存在する。なので時代や社会を風刺するロシア映画を見る時は、その作品がソビエト映画なのかロシア映画なのかを理解しておく必要がある。
独裁者であったスターリンの死後、民主主義へと移行する「雪解け」と言われる時代には様々なジャンルの映画が製作されるようになる。この頃に現れたのがロシア映画の父とも言えるアンドレイ・タルコフスキーである。タルコフスキーはデビュー作『僕の村は戦場だった』(1962)でベネチア国際映画祭で金獅子賞を獲得する程の才能であった。徹底して芸術至上主義を貫くその作風はロシア映画の現在にも根付いている。
ここで「ロシア映画は世界で最も芸術的である」と言わせてほしい。というのもロシア映画においてタルコフスキーの存在はフランスのヌーベルバーグにも等しいからである。ロシア映画の難解というイメージはタルコフスキー作品のイメージそのもので、その作風はしばしば「ロシア的」という言われ方をする。
もちろんロシア映画が芸術的なのはタルコフスキーの影響でだけではない。国土のほとんどが極寒の不毛の大地なせいか映画のテーマに死生観がよく持ち込まれること、広大な自然が圧倒的な映像美を生み出すなどの理由もある。
ソビエト崩壊後のロシア映画は芸術性よりも利益が追求される傾向が強くなったが、”New Tarkovsky” (新しいタルコフスキー)と呼ばれるアレクサンドル・ソクーロフ 監督の『ファウスト』(2011)や、アンドレイ・ズビャギンツェフの『父、帰る』 (2003)は難解な作品でありながらベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞している。世界的な評価を受けるのはやはり「ロシア的」な作品なのだ。
2015年に公開されたロシアの巨匠アレクセイ・ゲルマン監督の遺作『神々のたそがれ』はタルコフスキーの『惑星ソラリス』(1972)を彷彿とさせる難解かつ社会風刺的なSF作品だった。こちらも2015年公開の作品だが、新鋭監督アレクサンドル・コットの『草原の実験』にはタルコフスキーの遺作『サクリファイス』(1986)を想起させる芸術性があった。現在までロシア映画の中にはタルコフスキーの血が色濃く流れている。
チェコ映画
 チェコという国は、一党独裁の社会主義であるチェコスロバキアから1993年に民主化を伴って生まれた国である。映画産業が始まったのはチェコスロバキア時代よりさらにさかのぼる1898年、オーストリア=ハンガリー帝国の時代である。現在チェコ映画というと、これらすべての時代の映画を指す。
チェコという国は、一党独裁の社会主義であるチェコスロバキアから1993年に民主化を伴って生まれた国である。映画産業が始まったのはチェコスロバキア時代よりさらにさかのぼる1898年、オーストリア=ハンガリー帝国の時代である。現在チェコ映画というと、これらすべての時代の映画を指す。
チェコの首都プラハ郊外には、ヨーロッパ最大の映画スタジオ・バランドフがあるが、これは1933年に初代大統領ヴァーツラフ・ハヴェルの伯父であるミロシュ・ハヴェルによって建てられたものである。国を挙げて映画に力を入れた時代であり、映画とほかの芸術を組み合わせた実験的なアバンギャルド映画の製作や映画批評が盛んに行われた。第二次世界大戦以前に芸術性の高い作品が生まれ、チェコ映画は「撮影の美しさ、トーンの正確さ、大胆さを排除しない真摯な態度、自然と民間伝承的な農民あるいは都会の庶民生活へのリアルな感覚」と言われた。
しかし第二次世界大戦が始まると、ナチス・ドイツの占領下でプロパガンダ映画ばかり製作されることとなる。また1950年代前半になると社会主義体制が確立され、映画製作の自由は制限され、再び社会主義リアリズムを描いたプロパガンダ映画が製作され始める。
ただ、終戦から社会主義体制の確立までのわずかな期間に撮られたチェコ映画は本来の力を感じさせるものであった。フランチシェク・チャープの『翼のない男たち』(1946年)はカンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞し、20世紀初めの労働者闘争を描いたカレル・シュテクリーの『シレーナ』(1947年)はベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞している。
その後、社会主義の影響で停滞していたチェコ映画だが、ソ連が独裁者であったスターリンの死に伴い民主主義へと移行する「雪解け」と言われる時代が追い風となって、共産主義やスターリンを批判するチェコ・ヌーベルバーグというムーブメントが生まれた。
チェコ・ヌーベルバーグ時代の作品は国際的評価も高く、1965年から4年連続でアカデミー外国語映画賞にノミネートされ、うち『大通りの店』『厳重に監視された列車』の2作は受賞を果たしている。しかし、チェコ・ヌーベルバーグは民主化に対するソ連の軍事介入(チェコ事件)によって程なく終焉を迎える。
これによりチェコ・ヌーヴェルヴァーグの監督たちは国外へ亡命し、国内の映画は再び長い低迷期を迎える。1980年代にはミロス・フォアマンなどの監督が再び国内での撮影を試みた。アカデミー賞の作品賞や監督賞など、数々の映画賞を受賞したフォアマンの『アマデウス』(1984年)はその一つであるが、厳密にはアメリカ映画である。1990年にベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞した『つながれたヒバリ』はチェコ・ヌーヴェルヴァーグの一員であったイジー・メンツェル監督の作品で純血のチェコ映画であったが、1969年に製作された作品であり、共産主義体制崩壊後にようやく評価された形となった。
そしてようやく1993年に民主化し、チェコ共和国が誕生する。これ以降若い世代の監督たちによる新しいチェコ映画の再生が模索される。ヤン・スヴェラーク監督の『コーリャ 愛のプラハ』(1996年)はアカデミー外国語映画賞を受賞するなど、現在までチェコ映画は再び芸術性と国際的な評価を取り戻した。
2015年に日本でも公開されたヤン・スヴェラーク監督の『クーキー』は、国内で大ヒットし世界でも評価されている。この作品は一見ディズニー映画のようだが、チェコの人形劇は娯楽ではなく文化として確立されており、歴史的にも重要な意味を持っていた。
永きに渡ってオーストリア・ハンガリー帝国からの支配を受けてきたチェコではドイツ語を話すことが強制されていた。自分たちの言葉を奪われ、文化を奪われ、他国の政治を身勝手に押し付けられてきたチェコの人々が、自らの拠り所としたのが人形劇。人形劇だけはチェコ語の使用が認められていたのだ。
人形劇と映画の組み合わせは、チェコ映画の創成期に生まれたアバンギャルド映画の手法であり、かつて東ヨーロッパの映画産業の中心地であった姿を想像させる作品である。
ポーランド映画
 日本で一番有名なポーランド映画はカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した『戦場のピアニスト』(2002)だと思うが、あの映画がポーランド映画だと知る人はあまり多くいないはずだ。
日本で一番有名なポーランド映画はカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した『戦場のピアニスト』(2002)だと思うが、あの映画がポーランド映画だと知る人はあまり多くいないはずだ。
ポーランドはドイツとロシアに挟まれ、ファシズムと社会主義に翻弄され、国土を分割され地図から消えたこともある不幸な歴史を持つ。ナチス治下ではあのアウシュビッツの悲劇に遭った国だ。首都ワルシャワでは罪のない女、子供が、花でも摘むかのように簡単に殺された。
こうした歴史が引き金となり、「ポーランド派」と呼ばれるヨーロッパで初となる反社会主義の芸術ムーヴメントが誕生した。これはイタリアのネオレアリズモの影響を強く受けた動きであったが、「ポーランド派」は厳しい検閲の中で作品を生み出していくこととなる。
「ポーランド派」を代表する作品には、ワルシャワ蜂起時のレジスタンスや戦後共産化したポーランド社会におけるその末路を描いたアンジェイ・ワイダ監督の抵抗三部作『世代』『地下水道』『灰とダイヤモンド』があり、カンヌ、ベネチア国際映画祭で高い評価を受けた。
ポーランド映画は特に難解だと言われている。歴史に翻弄され、検閲が恒常的に行われていた社会で、高度な表現を大衆の方で読み解くということが日常的に行われていたことと、ポーランドの芸術に歴史文学が深く根付いているという点だ。これらのことから、ポーランド映画は極めて芸術的な評価を受けることが多い。
ポーランドは映画先進国である。ポーランドにはウッチ映画大学(48年創設)、カトヴィツェ映画大学(78年創設)、俳優を育成するワルシャワ演劇大学など多数の教育機関が存在し、その水準も高い。それはひとえに、国にとって映画の持つ役割がどれほど大きかったのかを示している。
しかし1980以降の体制転換の折、ポーランド映画は長い低迷の時を迎えることとなる。組織の混乱による映画製作環境の悪化と、経済的困窮による予算不足が原因であった。そんな中1981年に、「ポーランド派」として抵抗三部作を手掛けたアンジェイ・ワイダ監督が『鉄の男』でカンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞しているが、1980年に起きたグダニスク造船所でのストライキに始まる連帯運動を描いた反体制的な内容から、ポーランド映画人協会長の職を追われることとなった。
ポーランドの映画史を見渡すと、『戦場のピアニスト』がポーランド映画らしい作品であることがわかると思う。
アジア
日本映画
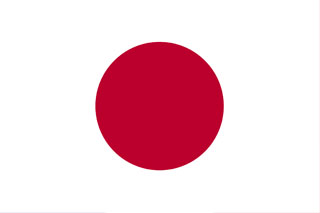 日本映画は世界的に見れば、スタジオ・ジブリを始めとするアニメーションのレベルの高さが最も特徴的である。ディズニーと比較されることもあるが、テーマの深さ、ストーリー性、オリジナリティ、どれをとっても抜けている。
日本映画は世界的に見れば、スタジオ・ジブリを始めとするアニメーションのレベルの高さが最も特徴的である。ディズニーと比較されることもあるが、テーマの深さ、ストーリー性、オリジナリティ、どれをとっても抜けている。
またマンガも同様に世界最高レベルの文化であるため、最近ではマンガを原作とした映画が多く撮られるのも日本映画の特徴である。
しかしこうした現在のイメージ以前に、日本映画は早くから世界で評価されていたことを知っておいてもらいたい。その先駆けとも言えるのが黒澤明の『羅生門』(1950)である。この作品はベネチア国際映画祭で最高賞である金獅子賞を受賞したのみならず、ベネチア国際映画祭50周年記念行事で歴代グランプリ作品中最高の作品「獅子の中の獅子」栄誉金獅子賞までも受賞した。
そして日本映画は『羅生門』を皮切りに、ベネチア、ベルリン、カンヌの世界三大映画祭で最高賞を受賞している。アジア映画の中では早くから世界的に評価されていたのが日本映画だ。
ベネチア国際映画祭金獅子賞
- 1951年『羅生門』黒澤明
- 1958年『無法松の一生』稲垣浩
- 1997年『HANA-BI』北野武
ベルリン国際映画祭金熊賞
- 1963年『武士道残酷物語』今井正
- 2002年『千と千尋の神隠し』宮崎駿
カンヌ国際映画祭パルム・ドール
- 1954年『地獄門』衣笠貞之助
- 1980年『影武者』黒澤明
- 1983年『楢山節考』今村昌平
- 1997年『うなぎ』今村昌平
ヨーロッパの映画祭で評価されることが多いことからも、日本映画はヨーロッパ映画に近い空気を持っているとも言える。いわゆるハリウッド映画のような派手なアクションなどは少ない。銃社会でないことも理由であるが、これはやはり日本人独特の美的感覚によるところが大きいと思われる。古くから「わびさび」の感覚を大切にしてきた感性は映画にも表れている。
その代表的な作品がアカデミー賞外国語映画賞を獲得した唯一の日本映画『おくりびと』(2008)だろう。死んだ人を送り出す納棺師を描いた作品だが、その所作の美しさは日本的であり、外国人の心にも響いた。
韓国映画
 近年、急速な成長を続ける韓国映画市場。その規模はもはや日本とほぼ横並びのところまできている。そのきっかけとなったのが、『シュリ』(1999)と『猟奇的な彼女』(2001)の大ヒットと国際的な成功だった。しかし現在、この2作品は韓国の歴代観客動員数で圏外となっている。これが韓国映画市場の急成長を物語っている。
近年、急速な成長を続ける韓国映画市場。その規模はもはや日本とほぼ横並びのところまできている。そのきっかけとなったのが、『シュリ』(1999)と『猟奇的な彼女』(2001)の大ヒットと国際的な成功だった。しかし現在、この2作品は韓国の歴代観客動員数で圏外となっている。これが韓国映画市場の急成長を物語っている。
現在、韓国の歴代観客動員数で1位と2位になっているのが2014年の『バトル・オーシャン 海上決戦』と『国際市場で逢いましょう』である。この2作品は『シュリ』の観客動員数を2倍以上上回るほどの成功を収めている。
しかし、この『バトル・オーシャン 海上決戦』の歴代観客動員数1位という記録は日本人としては複雑な思いもある。『バトル・オーシャン 海上決戦』は16世紀末、豊臣秀吉による朝鮮侵攻の一つである慶長の役、鳴梁(ミョンリャン)海戦を描いたものだ。軍船330隻の倭軍を朝鮮水軍はたった12隻の戦力で迎え撃ち、これを撃破したという内容だが、史実は違う。
韓国では朝鮮水軍が日本水軍に勝利した戦いとして認識され、朝鮮水軍を率いたイ・スンシン将軍は英雄として扱われているが、これは鳴梁海戦の初戦だけを切り取ったに過ぎない。大局を見れば、朝鮮水軍は遠方まで撤退したことで朝鮮水軍の基地である全羅道右水営や対岸の珍島の攻略を許し、日本水軍の侵攻は成功している。脚色と言ってしまえばそれまでかもしれないが、『バトル・オーシャン 海上決戦』の大ヒットの裏には少なからず抗日感情が影響している。
それも軍国主義時代の日本による植民地支配が国民に根深い抗日感情を抱かせってしまっているのだろう。韓国にとって日本は、ヨーロッパにおけるドイツのような存在なのかもしれない。映画においても日本が厳しい検閲を敷いた歴史がある。それはおそらく韓国映画の発展を妨げるものであったはずだ。
しかし2000年代以降、韓国映画は世界三大映画祭でも評価されるようになり、市場の成長に伴って芸術性の高い作品が生まれている。2012年のキム・ギドク監督の『嘆きのピエタ』はついにベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞している。これは韓国映画史上初となる世界三大映画祭での最高賞受賞という快挙であった。これは日本人としても喜ばしいことである。
間違いなく韓国を代表する映画監督であるキム・ギドクだが、彼の作品は韓国映画の主流ではない。『うつせみ』(2004)は主人公のセリフが一切ないという奇妙な作品であったが、ベネチア国際映画祭で銀獅子賞(監督賞)を受賞し、隠遁生活中の自身の姿を映したドキュメンタリー『アリラン』(2011)はカンヌ国際映画祭ある視点部門で作品賞を受賞している。キム・ギドクは、ヌーベルバーグ以降のフランス映画に「新しい波」をもたらしたと言われるレオス・カラックスに影響を受けたと語るが、その映像や難解さは独特の表現と言える。
今の韓国映画にはキム・ギドクのような監督もいるが、主流はハリウッドの流れを汲むエンターテイメント性の高い作品だ。また日本から独立後、北緯38度以北(北朝鮮)をソ連に、以南(南朝鮮)をアメリカにそれぞれ占領されたことから国を分断された歴史を持ち、南北統一のため起こった朝鮮戦争では朝鮮半島のほとんどが戦場と化したことで深い傷跡を残した。この歴史をしばしば人間ドラマの中に落とし込んで見せるのも韓国映画の特徴の一つである。
中国映画
 世界でも最も厳しい検閲にさらされているのが中国映画だ。1949年から現在まで共産党の一党独裁体制が続く中国だが、当時はマスメディアの統制を強化するため1949年以前の中国映画、香港映画、アメリカ映画の上映を禁止しし、さらに政府は映画を重要な大衆向け芸術であることを理解し、プロパガンダとしても利用した。
世界でも最も厳しい検閲にさらされているのが中国映画だ。1949年から現在まで共産党の一党独裁体制が続く中国だが、当時はマスメディアの統制を強化するため1949年以前の中国映画、香港映画、アメリカ映画の上映を禁止しし、さらに政府は映画を重要な大衆向け芸術であることを理解し、プロパガンダとしても利用した。
こうした中国の歴史は自由なイデオロギーで映画を制作することを困難にし、他の先進国に比べ映画の発展をかなり遅らせている。近年急激な経済成長を遂げたことで中国の映画市場は、日本を抜いてアメリカに次ぐ世界第2位まで成長している。そして近い将来、世界一の映画市場になると見られているが、市場の規模に対して映画も現在進行形で急速に発展している。
実際、中国映画が過去の社会主義リアリズムから脱却し、世界的に評価されるようになったのは1980年代末である。鮮やかな映像美を得意とするチャン・イーモウ監督の『紅いコーリャン』(1987)はベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞し、中国国内でも社会現象となった。またチェン・カイコー監督の『さらば、わが愛/覇王別姫』(1993)はカンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞し、シェ・フェイ監督の『香魂女 湖に生きる』(1993)はベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞した。
中国映画史において「第五世代」と呼ばれるこれらの監督たちは、この時代に世界三大映画祭の最高賞を受賞し、ここから現在に至るまで中国映画が世界で評価される基盤となった。先に紹介したチャン・イーモウ監督は『秋菊の物語』(1992)と『あの子を探して』(1999)でベネチア国際映画祭で金獅子賞を2度も受賞する快挙を達成している。
近年では「第六世代」と呼ばれる監督たちが、現実主義的なテーマと短期間に低予算で撮る手法でイタリアのネオレアリズモに似たムーヴメントを生んでいる。現代においてこうした動きが出てくることが、中国映画が遅まきに、そして急速に発展していることを証明しているように思う。
また、「第六世代」とは別に『グリーン・デスティニー』(1999)や『HERO』(2002)のような西洋的な好みに迎合した作品が興行的な成功を収めているのも特徴的だ。
しかし未だに厳しい検閲は残っており、政治的に微妙な作品は中国での上映を禁じられ、限られた予算で制作された中国映画の多くは香港や中国本土、台湾でのみ上映され、国際的な配給手段がないという現状である。
社会主義でありながら、経済は資本主義を取り入れた国家体制が中国映画を混沌とさせているのだ。その反面、人知れず名作が埋もれていたり、これから才能ある監督が生まれるなど、未知の可能性を予感させるのが中国映画だ。
香港映画
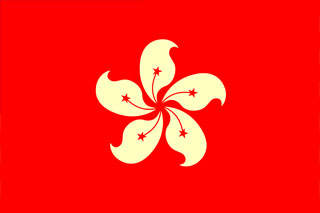 香港映画の特徴を知る上で明確にしておかなければいけないのが中国映画との違いだ。なぜ香港で製作された映画は中国映画ではなく香港映画と呼ばれるのか。
香港映画の特徴を知る上で明確にしておかなければいけないのが中国映画との違いだ。なぜ香港で製作された映画は中国映画ではなく香港映画と呼ばれるのか。
どこの国の映画史も、その国の歴史に大きな影響を受けているものだが、香港は第二次世界大戦 (1941–45) の間は日本に占領され、その後は1997年までイギリスの植民地であった。イギリスから中国に返還された後も、返還前の法律、制度、流通通貨などを返還後も向こう50年は変えないという「一国二制度」の原理の下、中国の一部でありながら「特別行政区」となった。これは世界でもかなり稀な例と言える。
こうした歴史が香港映画を中国映画を別物にしている。香港はイギリスの植民地時代から資本主義で、中国は社会主義という点からも違いは表れている。
中国本土の映画が常に政治状況に大きく左右されるのに対して、香港はイギリスの植民地であったためにイデオロギーからは自由であり、商業で栄えた土地柄から商業主義に徹した徹底娯楽映画で特異な発達をするようになった。中国映画と混同しがちだが、カンフー映画の原点は香港映画であり、その中で生まれた香港映画を代表するスターがブルース・リーやジャッキー・チェンだ。
娯楽映画に特化した香港映画の特徴をよく表しているのが、クエンティン・タランティーノ監督が「ぶっちぎりに凄い映画だ」と絶賛するほどのエンターテイメント映画『少林サッカー』(2001)とその続編的作品『カンフーハッスル』(2004)だ。アメリカでも大ヒットし、この2本は香港映画の歴代興行収入の1位と2位を占めている。
その他
インド映画
 年間の映画の制作本数が世界一を誇る映画大国インドだが、映画が大衆に愛されていると同時に、多言語国家であるためヒンディー語を始めとする23の公用語で映画が製作されることでも製作本数が多くなっている。インド文化に精通している人間なら言語や登場人物の名前から宗教、社会層や経済状態などの情報を受け取ることが可能な場合もあるという。日本で公開されるインド映画のほとんどはヒンディー語である。言語ごとに独自の発展を遂げたインド映画だが、ここではインド映画に共通する特徴を挙げてみたいと思う。
年間の映画の制作本数が世界一を誇る映画大国インドだが、映画が大衆に愛されていると同時に、多言語国家であるためヒンディー語を始めとする23の公用語で映画が製作されることでも製作本数が多くなっている。インド文化に精通している人間なら言語や登場人物の名前から宗教、社会層や経済状態などの情報を受け取ることが可能な場合もあるという。日本で公開されるインド映画のほとんどはヒンディー語である。言語ごとに独自の発展を遂げたインド映画だが、ここではインド映画に共通する特徴を挙げてみたいと思う。
ヒンディー語の娯楽映画は、その制作の中心地ムンバイーの旧名ボンベイとアメリカのハリウッドをもじって、「ボリウッド」の愛称で呼ばれるが、「ハリウッドの劣化版」という皮肉として使われることもある。日本では「マサラムービー」と呼ばれ、近年公開本数は増加するちょっとしたブームとなっている。
世界一の製作本数を誇るため、もちろん芸術性の高いものや難解なものもあるが、基本的には「ボリウッド」に代表する娯楽映画が多く、それらの作品にはしばしば歌と踊りのミュージカルシーンが挿入されることが特徴的である。また3時間前後の大作が多く、上映時間が長いことでも知られる。インド映画のこうしたスタイルは日本人にとって免疫がないと馴染みづらいかもしれない。
しかしインド映画を見る上で、最も重要で日本人に馴染みがないのが「ラサ」と言われるインドの伝統的な美学だ。「ラサ」とは恋愛、滑稽な笑い、悲しみ、怒り、勇ましさ、恐れ、嫌悪、驚き、平和の9つの感情のことで、映画を含む芸術の多くで重要視される。
普通芸術に触れた時、そこで生まれる感情は人それぞれなのだが、インドではその芸術には受け手の感情を超越した感情が絶対的に内在すると考えられている。観客に悲しみを感じさせるべきところで怒りを感じさせてはいけないのだ。よって「ラサ」の感情表現は観客を強制的に共感させ一種のカタルシス(鬱積した感情の浄化による快感)へと誘うとされる。
インド映画でもこの「ラサ」という考え方が重要視されるため、免疫がないと感情表現に違和感を感じるかもしれない。逆に「ラサ」を理解していれば日本人であってもカタルシスを共有できるはずだ。
また、インド映画は劇場で見ることを至上目的として製作されていることも特徴の一つである。インド映画は劇場での収入が7割を占めてる。このため映像、色彩、音響、すべての演出は劇場での上映を優先させた本来映画が在るべき作りがなされている。
そうした映画の在り方の延長線上か、インド映画には必ず途中でインターミッションと呼ばれる休憩が入る。インド映画以外でも無理矢理インターミッションが入るほど定着した文化となっている。これは、トイレ休憩や、劇場の収入である飲食物の購入のために確保された時間なのだが、鑑賞中の映画のこれまで、そしてこれからについて同伴者とあれこれ語れる楽しい時間でもある。
ぜひ日本でもインターミッションが定着してもらいたいと思うのは僕だけだろうか。本当に映画を楽しんでいる国がインドである。






